海洋環境の保護対策、大気汚染防止及び省エネ対策、二酸化炭素排出削減等を目的としたモーダルシフト、輸送の安全確保等を推進します。
1)海洋汚染防止に関する取り組み
船舶による汚染防止については、国際条約「MARPOL 73/78条約」によって世界規模での統一規制が行われ、我が国では「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に取り入れられています。
国際条約「MARPOL条約」附属書Ⅴの改正により、同附属書で明確に許可されない全ての種類の廃棄物の海洋への投棄が平成25年1月1日から禁止されました。
特に、海洋環境に有害な物質(貨物残留物等)の受け入れ施設や処理体制等については、今後適切に対応できるよう必要に応じ行政当局に要請します。
平成30年第196回国会において「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律」(シップリサイクル法)が可決しました。今後の発効後において、内航船舶に経済性を含めて過度の負担とならぬよう行政当局に働きかけます。
HNS 条約の発効(バンカー条約とレックリムーバル条約は既に発効済み)と併せて、我が国による3条約批准の予定につき行政当局と密接な情報共有をはかり、それらが船舶油濁損害賠償法等の国内法に取り入れられる際の内航海運への影響とメリットにつき整理して、関係者の理解と協力を要請します。
2)海洋汚染等・海上災害防止の手びき(未来に残そう美しい海)

国際条約の規則と解釈について現場で理解しやすいよう解説したもので、組合員や関係者が海洋環境の保全により一層取り組めるよう、平成22年この手びきを作成しました。
3)大気汚染防止に関する取り組み
MARPOL条約上の2020年1月1日より適用開始となった硫黄酸化物(SOx)規制強化(使用燃料油の硫黄分含有量が0.5%以下に規制された)に伴う低硫黄燃料油使用等への対応については、内航船舶が就航する各港で安全な性状の適合油が適正価格で安定的に供給されているかについて調査し、問題点の洗い出しを行い、適切な対応が行われるよう必要に応じて行政当局に働きかけを行います。
4)地球温暖化に関する取り組み
環境共創イニシアチブの支援事業を積極的に活用し、企業単位としての環境保全、省エネ効果による二酸化炭素の削減及び改善活動が行われるよう同制度の周知に努めるとともに、日本経済団体連合会の「低炭素社会実行計画」に参画し、ボランタリープランとして平成32年度の二酸化炭素排出量の数値目標を立て、業界団体として継続して取り組んでいます。
5)内航海運における使用燃料油、潤滑油に関する実態調査報告書
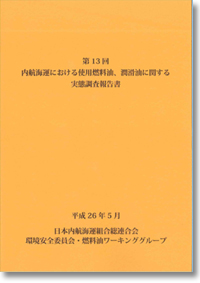
平成28年8月に『第14回内航海運における使用燃料油、潤滑油に関する実態調査報告書』作成のため、アンケート調査を開始しました。本報告書は平成29年7月頃に作成し、配布予定です。
この報告書は、組合員に対する技術的な指針となるよう、環境安全委員会・燃料油ワーキンググループが過去30年に亘り2~3年毎にアンケート調査等を実施し、内航燃料油の使用実績から燃料油に起因すると考えられる障害事例、A重油・C重油の一般性状の傾向、主機・発電機・ボイラー等の各種データ、潤滑油関係、船型・船種・船齢別の航海速力推移、粗悪燃料油に起因すると考えられる機関障害を取り纏めています。
環境問題に関する各種規則が厳しくなる中で、機関長・士のみならず事業責任者及び内航海運に関心を持たれている方々の参考資料として提供しています。
6)運輸安全マネージメント制度の導入
運輸事業者の安全管理体制構築のための法律(運輸安全一括法)が制定され、平成18 年10 月の施行と同時に「運輸安全マネージメント制度」が導入されました。これにより、運送事業者は「安全管理規程」「運航基準」「事故処理基準」の作成、さらに「安全管理統括者」を設置して、経営トップから現場まで一丸となった安全への取り組み体制を構築しました。
本制度の対象となる事業者は「運輸マネージメント評価」を受け、安全への取り組み体制の見直しを図っていく必要があるため、当総連合会としても、本制度がより実効性のある制度となるよう安全管理規程の見直しと啓蒙活動に努めています。
Copyright © 2026 Japan Federation of Coastal Shipping Associations